「立春」と聞くと、
「いよいよ春!」という気分になりますが、
実際はまだまだ寒い日が続きますよね。
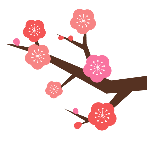
むしろ「一番寒いのは今じゃない?」と感じることも。
なぜ暦の上では春なのに、
体感的には冬真っ只中なのでしょうか?
「立春」は二十四節気の第1。
太陽の動きをもとに決められているそうです。
今年は1日早くなりましたね。
立春は、昼の長さが徐々に伸び始めるタイミングに
設定されているため、
気温とは必ずしも一致しないそうなのです。
立春を迎えたのに大雪が降ることだってありますね。
つまり、立春=毎日ポカポカ陽気とは
限らないわけですね。
啓蟄、虫たちは本当に出てくるの?
「啓蟄(けいちつ)」とは、
冬ごもりしていた虫たちが地中から出てくる頃、
とされています。
今年は3月5日だそうです。
啓蟄の「啓」は「開放」、
「蟄」は「虫の冬ごもり」を意味するらしいです。
(私も今年、初めて知りました💦)
実際にこの時期に虫がワラワラと出てくる光景、
みなさんは見たことありますか?
啓蟄に虫たちが目覚めるかどうかは、
その年の気温によるそうなのです。
日本各地の気象データを見ると、
啓蟄(3月上旬)はまだ気温が低いことが多く、
本格的に虫が活動を始めるのはもう少し先みたい。
特に地中にいる虫たちは、
地面が十分に温まらないと出てこられません💦
日当たりの良い場所では
小さなハエやアリがチョロチョロと
動き始めることもあるみたいです。
昔の人々は、
虫の活動を観察しながら
季節の移り変わりを感じていたんですね。
今のように天気予報がなかった時代、
自然の変化を知ることは
とても大事な知恵だったのですね。
せっかくなら、
子どもたちと「春探し」をしてみませんか?
「立春だけど、今日の気温は春?」
「啓蟄の日、虫さん出てくるかな?」
「春を見つけて(感じて)みよう!」
(ぽかぽかしてるね~。梅がさいてるね。
ウグイスが鳴いてるね。などなど。)
こんな風に問いかけながら、
身近な自然を観察すると、
子どもたちもワクワクしながら
季節の変化を感じられるはずです。
「へ~っ!」と思ったら、
ぜひ子どもたちにも伝えてみてくださいね!




